 ALL NIPPON PRODUCERS ASSOCIATON ALL NIPPON PRODUCERS ASSOCIATON |
|
|
★第29条第1項★ |
|
|
| 法人著作権は国辱モノ |
著作権委員長 |
| 第1回公開研究会報告 |
針生 宏 |
|
柳原敏夫弁護士による現行著作権法の指摘は、プロデューサーの権利運動を勇気づける示唆に富んでいた。
19世紀末いらい、世界の近代法はすべて産業や資本などの経済邸強者に対して弱者である個人の権利を守るという方向。日本でも労働基準法や借家法はその流れに沿っていたのに、著作権法だけは近代法の精神にも時代の趨勢にも逆行していた。
法人に著作権を認めたこと、とくに映画著作物については第29条第1項で明らかに強者である法人制作者の立場に偏り、弱者である著作者から契約さえなしに権利を奪い取れるという条項は、世界に例を見ない時代錯誤で国際的な批判の的になっている。 |
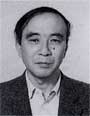 |
著作行為をするのも、創作するのも、法人ではなく個人。
現に特許法では、法人が金を出そうと雇用主だろうと、特許権は直接開発に当たった個人にしか認められていない。
著作権法も、早くその方向を目指して、世界に顔向けできないような現状から抜け出すべきである。
著作権は著作個人にある、ということがすでに定着して久しいヨーロッパなどでは、さらに一歩進んで、その権利をいかに有効に実現させるか、という実行段階での保障に法律的な焦点が移りつつある。
ドイツの連邦議会に上程されている「著作者契約法案」は、世界の注目を集める画期的な内容。権利はあっても個々の契約交渉では弱い立場に立たされる著作者・実演家に、最低限の報酬と条件を法律で保障し、法廷報酬請求権制度によって著作物の利用者に支払いを義務づけようとしている。
日本でも音楽の分野では、著作者・実演家が自分たちの権利や利益を完全に貫きながらレコードを自主制作できるという、既成の企業や団体とは全く性格の違うグループが誕生し、参加者支援者の輪が急速に広がりつつあるという。(映画でも、スタッフに契約で著作権を明示して制作に入るグループが誕生したと聞いた)
プロデューサーも、個々の実務上で当然の権利実現に努めながら、著作権法の改正を目指すべきではないか。 |
  
|